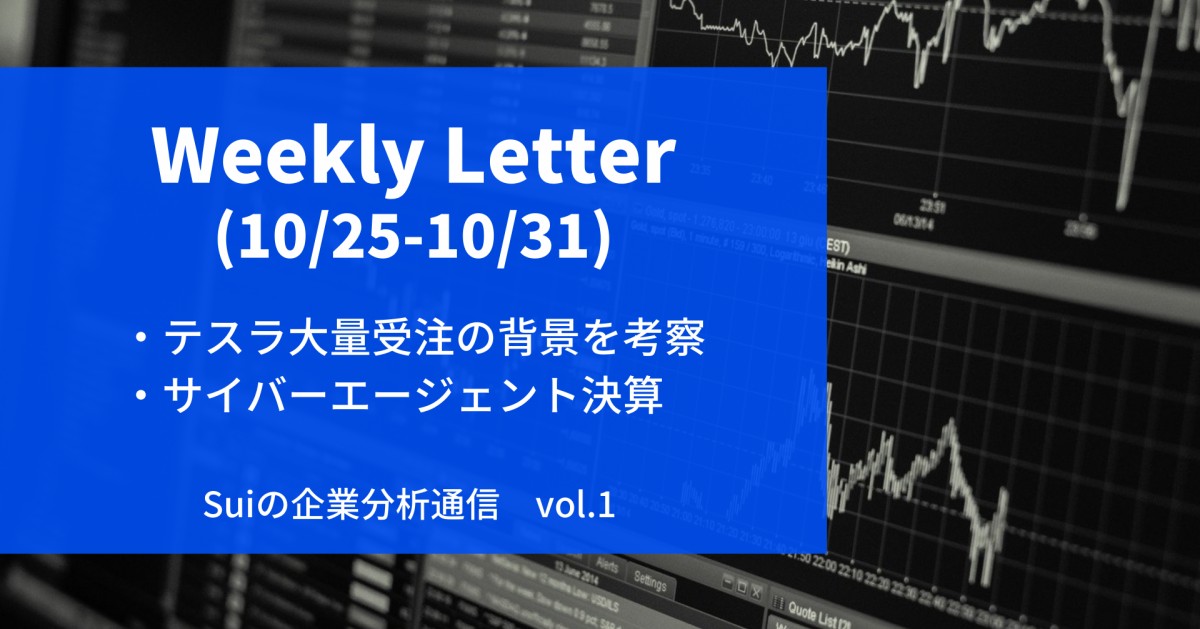Vol.2 Weekly Letter(11/1-11/7)
こんにちは、Suiです。
このWeekly Letterでは1週間で気になったニュースや記事などを読者の皆さんに紹介していきたいと思います。重要なニュースや役立つ記事などを私Suiがピックアップして、解説などを交えながらお届けする内容になっています。
今後、変更する可能性はありますが、トピックは以下の通りです。
-
注目ニュース
-
特集(企業分析のノウハウなど)
-
気になる決算、企業
-
参考になったツイート、記事
-
おすすめ本紹介
-
アイデア、雑談、その他
1.注目ニュース
先週(11/1-11/7)の注目ニュースを取り上げて、その記事の解説や自分の感想、今後の見通しや予想などを書いていきます。できるだけマーケットでの重要ニュースを取り上げたいと思うので、皆さんの振り返りにも役立つと思います。
気候変動関連、COP26
まずは気候変動関連で重要なCOPについて。地球温暖化対策の国際的な枠組みを決める会議の中でCOPは最高決定機関とされています。今回のCOP含め、日経の記事が分かりやすくまとまっています。
COP26の主なテーマは①2030年までの温暖化ガスの削減目標の引き上げ②国際排出枠取引制度の詳細なルール決定③環境対策のための途上国への資金支援――などだ。各国はCOP26に向けて排出削減目標を引き上げてきたが、現時点では取り組みが不十分とされている。温暖化ガスのいっそうの削減に向け、石炭火力の早期廃止や電気自動車(EV)の普及、温暖化ガスを吸収する森林の保全といった具体策を議論する。
COP26で議長国を務める英国のジョンソン首相は、石炭火力発電所について先進国は30年まで、途上国も40年までの廃止を要求している。石炭火力発電に頼る中国やインド、米国、日本などは対応を迫られるが、合意は難しい状況だ。
G7各国は日本を除き、石炭火力の廃止や、排出量を実質ゼロにする目標年限を定めている。フランスは22年、英国は24年、イタリアは25年を掲げている。カナダは30年の原則廃止をめざしている。ドイツは石炭火力の廃止を38年までとしてきたが、9月の連邦議会選(総選挙)の結果、30年への前倒しをめざす動きが出てきている。日本は古くて効率の悪い石炭火力を減らすが、廃止時期は明示しておらず、世界からは消極的にも映る。
今回、特に石炭火力の廃止が取り上げられており、やはり世界的に石炭需要にとってはネガティブな状況は変わらないと思われます。各国の規制に先駆けて、欧米のアセマネでは石炭を使用した火力発電を行う企業への投資を行わないダイベストメントを既に表明している運用機関もあります。
電力不足などによる需要増加への期待から上昇していた石炭価格もこれを受けてか先物価格が下落しています。(もちろんこれまでの上昇の反動もありますが、長期的には需要は減っていくと思います)

電力10社の中間決算は7社が通期下方修正。燃調があるが燃料価格高騰の影響を受けたのが理由であった。
しかし東北電力、関西電力、九州電力のみコスト削減により、燃料高騰の影響を上回った。
他の燃料価格も大暴落すれば、徹底的に売り込まれた電力会社が注目される。
再エネの需要が高まっているのは事実で不可逆ですが、それによって資源価格の高騰、電力不足、インフレなどの影響が出ているんだと思います。 カーボンニュートラルへの過渡期なので、需要と供給のバランスが崩れて、短期的な価格変動が大きくなるのはこれからも頻発するのではないかと考えています。
脱炭素、気候変動関連のニュースについては、EnergyShiftというメディアが分かりやすい記事を発信しているので、いくつか紹介したいと思います。
セコイアのモデル転換
VCのSequoia Capitalが投資先の株式を上場後も保有できる新しいストラクチャーを発表し、話題になっています。
こちらの記事では、VCのビジネスモデルやこの新ストラクチャーが与える影響について分かりやすく解説されています。
つまり今回の話は、そもそも10年で償還しないといけないファンドサイクルって時代遅れだよねということを、業界を牽引してきた名門VCであるセコイア自らが宣言しているわけですね。新しいストラクチャーに変えることによって、創業者やLPとのインセンティブ構造を合致させることができるんじゃないかというわけです。
「融けていく未上場株市場と上場株市場の垣根」のパートはかなり自分も気になる部分で、アセマネへの影響が強まったり、アセマネとの競合化が進むのではないか?と考えています。従来の未上場銘柄=VC、上場銘柄=アセマネという棲み分けがどんどん無くなっていると思います。
今後の影響として、VCがIPOの時に売らず保有し続ける場合には、IPO直後の需給が変化する可能性が考えられます。
米国株 最高値を更新
今週は米国株(S&P500,NASDAQ)が最高値を更新し、続伸しています。要因として挙げられるのは、米金利の低下や好調な企業決算、インフレ懸念のピークアウトなどがあります。



投資家心理を表す指数は楽観的な水準を示していますが、強気要因として経済指標(ISM製造業景況感指数)の好調、インフラ法案、金利の水準などが挙げられています。

1点目:ナスダックのAdvanced-Decline Line(=上昇した銘柄-下落した銘柄数)はナスダックで底打ちして上昇基調、S&P500指数では改善を続けている。
←ナスダック
→S&P500指数
振り返りについては、下記のnoteが参考になります。毎週更新されているので、振り返りにとてもおすすめです。
また、少し長期的な話ではありますが、過去の米国株の上昇要因として大きいのは自社株買いとのデータもあるみたいです。
米国では役員報酬が株価連動報酬になっているケースが多く、自社株買いによって株価を上げるインセンティブが働きやすいと聞いたことがあります。この自社株買いが続くかどうか、つまりは米国企業の利益創出が続くかどうかにも少し注目した方が良いかもしれません。

・マルチプルの拡大=21%
・利益の成長=31.4%
・配当=7.1%
・自社株買い=40.5%
自社株買いがなければ、S&P500はATH付近の4600ではなく、2700に近いレベルになっていた。
2.特集、ノウハウ
特定のテーマについて深堀りした解説をしたり、企業分析に役立つ自分のノウハウなどを紹介したいと思います。経済誌のダイヤモンドや東洋経済でいう表紙にあたる特集記事みたいなイメージです。Twitterでは書ききれなかった内容や反応が良かったテーマについて取り上げたりしたいと思います。
---
今回の特集は、次の気になる決算の部分でユーザベースと任天堂の決算を深堀りしたいと思います。自分が決算を見る時にどこに注目しているかをこの2社の決算で解説します。
この記事は無料で続きを読めます
- 3.気になる決算、企業
- 4.参考になったツイート、記事
- 5.おすすめ本紹介
- 6.アイデア、コラム、その他
- 最後に
すでに登録された方はこちら